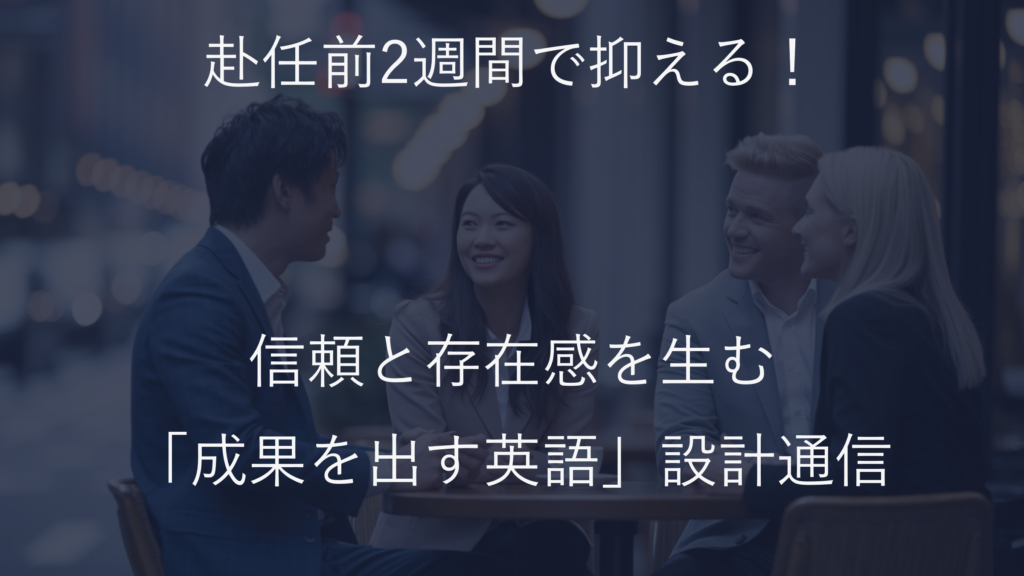野村耕平さん インドネシア駐在

大学卒業後、新卒でIT系の会社に入社するが倒産したため、シンガポールでキャリアを再スタート。日系企業の現地採用として経理に従事しながら米国公認会計士(USCPA)資格を取得し、その後は複数の米国系医療メーカーでFP&Aや管理会計の専門性を発揮。2020年から2022年には日系医療機器メーカーのインドネシア駐在員として、経理財務を軸に管理部門を幅広く担当。海外での勤務経験は通算12年以上。会計・財務を基盤に国際的なキャリアを歩んできた。
ーーどんな会社で、どのような役割で赴任されましたか?
日本の医療機器メーカーで、東京証券取引所のプライム市場に上場している会社です。
私は経営企画部という部署に属していて、ざっくり言うと子会社の業績管理や連結財務諸表の作成がメイン。そこに投資の実績管理や損益管理、予算と実績の差を見ながら調整していくような仕事も入ってきます。
子会社は百社以上あって、しかも孫会社まで含めると規模も国もバラバラ。中には売上規模が小さいところもあれば、相当大きいところもあります。そんなバラバラな会社をまとめて、数字の面でもガバナンスの面でも全体をきちっと見ていく、そういう部署でした。
その中で、私はインドネシアにあるかなり大きな拠点を担当することになって、経理・財務・購買・内部統制・税務など、いわゆる管理部門全般を任される駐在員として赴任しました。要は、現地の数字や内部管理をきちっと見ながら、日本本社とつなぐ役割ですね。
私は経営企画部という部署に属していて、ざっくり言うと子会社の業績管理や連結財務諸表の作成がメイン。そこに投資の実績管理や損益管理、予算と実績の差を見ながら調整していくような仕事も入ってきます。
子会社は百社以上あって、しかも孫会社まで含めると規模も国もバラバラ。中には売上規模が小さいところもあれば、相当大きいところもあります。そんなバラバラな会社をまとめて、数字の面でもガバナンスの面でも全体をきちっと見ていく、そういう部署でした。
その中で、私はインドネシアにあるかなり大きな拠点を担当することになって、経理・財務・購買・内部統制・税務など、いわゆる管理部門全般を任される駐在員として赴任しました。要は、現地の数字や内部管理をきちっと見ながら、日本本社とつなぐ役割ですね。

ーー赴任の話が出たとき、最初に感じたことは?
私の場合はちょっと特殊でして、もともと転職活動のときから「インドネシア駐在」が前提でした。
当時、「海外拠点に赴任できる人材を募集」という求人に応募して、その条件で採用されたんです。だから赴任の話が出たときは、「あ、来た来た。予定通りきたな」という感覚。
面接のときから「インドネシアに行ったら何ができるのか」「海外でのマネジメント経験はどう活かせるか」「海外生活や語学は問題ないか」みたいな話を、かなり具体的にしていました。
だから、突然海外行きを命じられてドキッとする人も多い中で、私の場合は逆にもう心の準備ができていたし、「やっとスタート地点に立ったな」という前向きな気持ちでした。
当時、「海外拠点に赴任できる人材を募集」という求人に応募して、その条件で採用されたんです。だから赴任の話が出たときは、「あ、来た来た。予定通りきたな」という感覚。
面接のときから「インドネシアに行ったら何ができるのか」「海外でのマネジメント経験はどう活かせるか」「海外生活や語学は問題ないか」みたいな話を、かなり具体的にしていました。
だから、突然海外行きを命じられてドキッとする人も多い中で、私の場合は逆にもう心の準備ができていたし、「やっとスタート地点に立ったな」という前向きな気持ちでした。
ーー英語に不安はありましたか?
英語については正直、不安はゼロでした。
というのも、私は赴任前からシンガポールで10年以上、外資系企業で働いていたんです。毎日英語で仕事をするのが当たり前の環境だったので、「英語でコミュニケーションできるかな…」という悩みはありませんでした。
というのも、私は赴任前からシンガポールで10年以上、外資系企業で働いていたんです。毎日英語で仕事をするのが当たり前の環境だったので、「英語でコミュニケーションできるかな…」という悩みはありませんでした。
むしろ不安だったのは、日本流の働き方や文化の方。前職はかなり日本的な社風で、しきたりや意思決定の仕方も独特です。海外式のスピード感や柔軟さに慣れていた自分としては、「これをどうハイブリッドしていくか」が大きなテーマでした。
実際、現地法人を運営する部分はこれまでの経験と大きく変わらないけれど、日本本社との関わり方は全く違う。そこをうまく橋渡しするのが自分の役割だな、と強く意識していました。
実際、現地法人を運営する部分はこれまでの経験と大きく変わらないけれど、日本本社との関わり方は全く違う。そこをうまく橋渡しするのが自分の役割だな、と強く意識していました。

ーー「やっておけばよかった…」と思ったことは?
振り返って「ああ、やっておけばよかったな」と思うのは、他の海外子会社とのネットワーク作りです。
赴任先や日本本社とのやり取りはどうしても一対一になりがち。でも、他の国の子会社も似たような課題や要求を抱えていて、「こういうときどうしてる?」と情報を共有できたら、もっと仕事がスムーズになったはずなんです。
例えば、日本本社からの依頼や要求って、実は他の国の子会社にも同じように来ていることが多いんです。そこで横のつながりがあれば、「うちはこうしてるよ」という情報をすぐにシェアできる。そうすれば余計な遠回りをせずに済むし、同じ立場の仲間がいる安心感もある。
実際、赴任直前には、同じように海外赴任する予定の人や一時帰国していた人たちと飲みに行ったりしてネットワークを広げようとしましたが、短期間ではなかなか深い関係になれませんでした。
同じ会社で、同じような立場で、別の国・別の拠点を担当している人たちって本当に貴重なんです。仕事の情報共有だけじゃなく、精神的な支えにもなりますから。そこをもう少し意識して、早めに動いておけば良かったな…と今でも思います。
ーー駐在中、「語学を学ぶ」ことに関して困ったことはありましたか?
私の場合、英語については全く問題がありませんでした。赴任前からシンガポールで10年以上外資系企業に勤めていて、毎日英語で仕事をしていましたから、「英語で業務を回せるか」という不安はゼロでした。
ただ、インドネシアの現地法人に行くとなると話は別で、やはり現地語=インドネシア語が必要になる場面が出てきます。マネジメント層の人たちはある程度英語を話せるし、日本とやり取りしているスタッフも英語力は高い人が多い。でも、スタッフ層、特に若手の社員になると英語はあまり得意じゃない人が結構いるんですよね。
インドネシアって、マネジメントは管理に専念していて、実務はほぼスタッフに任せきり、という組織構造が多いんです。それ自体は現地の文化なので問題ないんですが、私が何か細かい情報を知りたい時、まずマネジメント層に質問すると、その人たちはスタッフから聞いた話を私に伝える…つまり“伝聞の伝聞”になるわけです。これだと情報が欠けたり、意図が変わったり、本当に知りたいことにたどり着けないこともあります。時には「それ、あえて言ってないな」と感じるケースもありました。
そうなると、やっぱり自分で現場のスタッフと直接やり取りできる力=インドネシア語が必要になるんですよね。だから私は赴任して3か月目くらいには現地の先生を個人で雇ってインドネシア語を学び始めました。赴任前から自習も始めていたので、日常会話レベルは3か月でできるようになり、6か月も経つ頃には仕事のやり取りや突っ込んだ議論も問題なくできるようになりました。
やっぱり一度しっかり英語を学んだ経験があると、第2・第3言語の習得は取り掛かりやすいですね。勉強法のコツもわかっているし、英語と比較しながらインドネシア語を理解できる。これは本当に大きなアドバンテージでした。
ーー 逆に、赴任前に「これをしておいて良かった!」と思うことは?
ひとつ挙げるなら、「自己紹介スライドを作っておくこと」です。
これはシンガポールの外資系企業で学んだやり方なんですが、新しいマネージャーが着任すると、必ずチーム全員を集めて自己紹介をします。その時に口頭だけじゃなく、PowerPointでスライドを使うんです。
ポイントは、仕事の経歴やスキルももちろん載せるけど、それ以上に“人となり”が伝わる内容にすること。家族の写真や趣味の写真、休日の過ごし方など、プライベートな面を見せるんです。仕事の成果や経歴は、チームとして働いていく中で自然とわかりますし、着任直後にそれを長々説明しても「ちょっと堅いな」と思われてしまうこともある。むしろ、最初に見せづらいプライベートを出すことで、距離が一気に縮まるんですよね。
私もインドネシア赴任時にこれをやって、本当に効果を実感しました。言葉の壁があっても、写真はほとんど誤解なく伝わるし、「あ、ボルダリングやるんですか?」とか「子どもさん何歳ですか?」みたいに、仕事以外の会話のきっかけが自然に生まれます。これが後々のコミュニケーションの潤滑油になりました。
赴任前にこういうスライドを準備しておくのは、間違いなくおすすめできますね。
ーー実際の業務で「日本と違う」と感じたこと、苦労したことは?
そうですね…まず一番に感じたのは、仕事の“縄張り意識”がとにかく強いということですね。特に私がいたのはバックオフィス、いわゆる総務系や管理部門だったんですが、仕事がものすごく属人的なんです。
インドネシアの場合、スタッフレベルからマネージャーに昇進するケースはあまり多くなくて、マネージャー職は別の会社から転職してくる人が多い。なので、層が完全に分かれてしまっているんです。その結果、例えば「売掛金の管理」という仕事を担当した人は、入社してからずーっとそれだけをやっている。もうその分野に関しては誰よりも詳しいし、過去の経緯も全部頭に入っている。そこはメリットですよね。
でも、裏を返せばデメリットも大きい。例えばもし不正があっても他の誰にも見えないとか、その人が退職するとなると引き継ぎがとんでもなく大変になる。だからマネジメントとして赴任した場合は、そういう属人的な仕事をいかに共有させて、もし担当がいなくなっても回る仕組みにするか。そして、不正の温床にならないようにするか。ここは日本と大きく違って、最初から意識して進めないといけないポイントでした。
ーー現地スタッフとの関係づくりで成功したことや失敗したことは?
これはもう、「現地スタッフをひとりの人間としてちゃんと見る」ことに尽きると思います。
どうしても現地の人からすると、私は“日本人の◯◯さん”という肩書きで見られがちなんです。でも私は、できるだけ自分の個性や人となりを出すようにしました。「日本人マネージャー」じゃなくて、「こういう人間なんですよ」と。
同じように、スタッフのことも「インドネシア人」というひとくくりでは見ません。その人がどの地方の出身で、会社に何年勤めていて、家族構成はどうで、結婚記念日はいつか、子どもは何人いるのか…そういうことをちゃんと把握します。なぜかというと、インドネシアでは家族をとても大事にする文化があるからです。
突然会社を休むとか、勤務中に長時間電話している…日本だと「仕事中になんで?」と思うかもしれません。でも、大半は家族の問題なんです。日本的な「仕事第一」の考え方で押さえつけるよりも、家族の事情を優先してあげた方が、結果的に信頼関係が深まります。もちろん中には悪用する人もいますが、トータルで見れば、後からきちんと埋め合わせをしてくれる人の方が多い。
つまり大事なのは、仕事上のプロフェッショナル同士のつながりだけじゃなく、その人の背後にいる家族まで含めて関係を築くこと。それが現地での信頼関係のベースになると思っています。
どうしても現地の人からすると、私は“日本人の◯◯さん”という肩書きで見られがちなんです。でも私は、できるだけ自分の個性や人となりを出すようにしました。「日本人マネージャー」じゃなくて、「こういう人間なんですよ」と。
同じように、スタッフのことも「インドネシア人」というひとくくりでは見ません。その人がどの地方の出身で、会社に何年勤めていて、家族構成はどうで、結婚記念日はいつか、子どもは何人いるのか…そういうことをちゃんと把握します。なぜかというと、インドネシアでは家族をとても大事にする文化があるからです。
突然会社を休むとか、勤務中に長時間電話している…日本だと「仕事中になんで?」と思うかもしれません。でも、大半は家族の問題なんです。日本的な「仕事第一」の考え方で押さえつけるよりも、家族の事情を優先してあげた方が、結果的に信頼関係が深まります。もちろん中には悪用する人もいますが、トータルで見れば、後からきちんと埋め合わせをしてくれる人の方が多い。
つまり大事なのは、仕事上のプロフェッショナル同士のつながりだけじゃなく、その人の背後にいる家族まで含めて関係を築くこと。それが現地での信頼関係のベースになると思っています。

ーー文化の違い、コミュニケーション方法の違いを事前に知っておけば良かったと思うことはありますか?
うーん…正直、私の場合は特にはないですね。というのも、インドネシアに赴任する前からインドネシア人の友人がたくさんいて、彼らの宗教観や食生活、日常の考え方などはある程度理解していました。なので、赴任してから「えっ、そんな文化なの!?」と驚くことはほとんどありませんでした。
ただ、これはたまたま私がそうだっただけで、もしこれから赴任される方がいるなら、事前に現地の人と接点を持っておくのは本当に大事だと思います。日本国内でも留学生や技能実習生など、その国の方と知り合える機会って意外とありますし、可能であれば赴任前に現地へ出張や旅行をして、空気感を肌で感じておくと違います。
もうひとつ挙げるとすれば、食生活ですね。これは軽く見られがちですが、毎日のことなので意外と重要です。自分が現地の食事にどれくらい耐えられるか、楽しめるかを事前に知っておくと安心です。インドネシア料理は…まあ万人受けとは言えませんが、好きな人にはたまらない味。私は結構好きで、赴任後も特に困らず現地食を楽しめたので、その点は恵まれていたと思います。
ただ、これはたまたま私がそうだっただけで、もしこれから赴任される方がいるなら、事前に現地の人と接点を持っておくのは本当に大事だと思います。日本国内でも留学生や技能実習生など、その国の方と知り合える機会って意外とありますし、可能であれば赴任前に現地へ出張や旅行をして、空気感を肌で感じておくと違います。
もうひとつ挙げるとすれば、食生活ですね。これは軽く見られがちですが、毎日のことなので意外と重要です。自分が現地の食事にどれくらい耐えられるか、楽しめるかを事前に知っておくと安心です。インドネシア料理は…まあ万人受けとは言えませんが、好きな人にはたまらない味。私は結構好きで、赴任後も特に困らず現地食を楽しめたので、その点は恵まれていたと思います。
ーーマーケット情勢や組織状況など、実務の中で「これを事前に準備しておけば良かった」と思うことは?
これはですね…少し反則っぽいかもしれませんが、「正規のレポートラインを超えて相談できる人脈」を持っておくことです。
例えば、同じ会社の海外拠点で働いている仲間と仲良くなっておくとか、日本本社の関係部署に顔見知りを作っておくとか。こういう“横のつながり”があるだけで、現地で困った時の対応スピードがまったく違います。通常は、自分の上司経由で日本本社の上司同士がやり取りして…と回すので、時間もかかるし、話がややこしくなりがちです。でも、信頼できる人に直接チャットや電話で「これどうなってます?」と聞ける関係があれば、すぐに答えが返ってきます。
私も赴任直前に「これは関係しそうだな」という部署にあいさつ回りをして、顔だけでも覚えてもらうようにしました。そうすると、例えば赴任先でITシステムのトラブルが起きた時、日本側の情報システム部門に直接聞けるようになるんです。インドネシア拠点のIT担当は現地業務に特化しているので、日本本社の仕様や背景までは分からないことも多いんですよね。そこを直接つなげてもらえるだけで、本当に助かりました。
例えば、同じ会社の海外拠点で働いている仲間と仲良くなっておくとか、日本本社の関係部署に顔見知りを作っておくとか。こういう“横のつながり”があるだけで、現地で困った時の対応スピードがまったく違います。通常は、自分の上司経由で日本本社の上司同士がやり取りして…と回すので、時間もかかるし、話がややこしくなりがちです。でも、信頼できる人に直接チャットや電話で「これどうなってます?」と聞ける関係があれば、すぐに答えが返ってきます。
私も赴任直前に「これは関係しそうだな」という部署にあいさつ回りをして、顔だけでも覚えてもらうようにしました。そうすると、例えば赴任先でITシステムのトラブルが起きた時、日本側の情報システム部門に直接聞けるようになるんです。インドネシア拠点のIT担当は現地業務に特化しているので、日本本社の仕様や背景までは分からないことも多いんですよね。そこを直接つなげてもらえるだけで、本当に助かりました。

野村さんの話から見えてくるのは、「語学力」だけでは駐在員として成果を出せないという現実です。現地語の習得、人間関係の構築、横のネットワーク、そして文化的背景の理解。それらが揃って初めて、本社と現地をつなぐ役割を果たせます。
もしあなたがこれから海外駐在を控えている、または興味があるなら、野村さんの経験は大きなヒントになるはずです。特に「成果を出す語学力」をテーマにした実践的な知見は、現地でのパフォーマンスを左右します。
野村さんのように、赴任後すぐに動ける状態を作るための具体的なステップは、無料のメール講座「駐在力を整える7通メルマガ(成果を出す語学力について)」で詳しく解説しています。興味のある方は、今すぐ登録してみてください。
もしあなたがこれから海外駐在を控えている、または興味があるなら、野村さんの経験は大きなヒントになるはずです。特に「成果を出す語学力」をテーマにした実践的な知見は、現地でのパフォーマンスを左右します。
野村さんのように、赴任後すぐに動ける状態を作るための具体的なステップは、無料のメール講座「駐在力を整える7通メルマガ(成果を出す語学力について)」で詳しく解説しています。興味のある方は、今すぐ登録してみてください。